乙女たちのバスタイム
突然ですが、銭湯は好きですか。
シャワーしかないアパートに住んでいる人間にとっては、ひろい湯船に浸かれるというただ1点で、十分魅力的かもしれない。
京都に住んでいた頃はあちこちに銭湯があって、わたしもたまに利用していた。見ず知らずの人たちだが、誰かと一緒に入れるのがなんとなく楽しかった。
だがよく考えると、すごい。
人前で裸になるって勇気がいる。
われわれ日本人、街中では下着の線が見えることすら気にする民族だ。ブラの肩紐がはみ出さないかどうか、鏡で入念にチェックしたり。
だというのに、銭湯という空間ではその価値観が消えてなくなる。
「ゆ」と書かれたのれんをくぐって、番台さんにお金を払って、脱衣場に入ってしまえば、そこは異空間。外界とは異なるルールに支配される空間。スッポンポンのおばちゃんが、扇風機の前で涼んでいたりする。
そうとわかっていても、入っていきなり肌色が目に飛び込むと、ギョッとしてしまう。まだ半分街中の気分でいるからだろうか。
これ、ふしぎなことに、旅館の大浴場では感じない。
旅館の場合、門や渡り廊下など、コチラとアチラを分けるような仕掛けがちゃんとあるからだろうか、非日常の空間として線引きできる。
それに対して銭湯というのは、街中との境界線があいまいで、一応のれんで隔てられてはいるものの、なんの心構えもしないまますーっと入れてしまう。
すーっと入って、お、ハダカだ、とびっくりさせられる。
そういうふうに感じるの、わたしだけかなあ。
***
そんなことをつらつら考えつつ、大勢でお風呂に入るというのが日常だった頃を思い出す。銭湯が好きなのは、きっと誰かとお風呂に入った楽しい記憶があるからだ。
あの頃は、毎日寮生と一緒にお風呂に入っていた。うん、今から考えたら相当非日常。バスタイムなんて、ふつうならもっともプライベートに属する領域なのに。
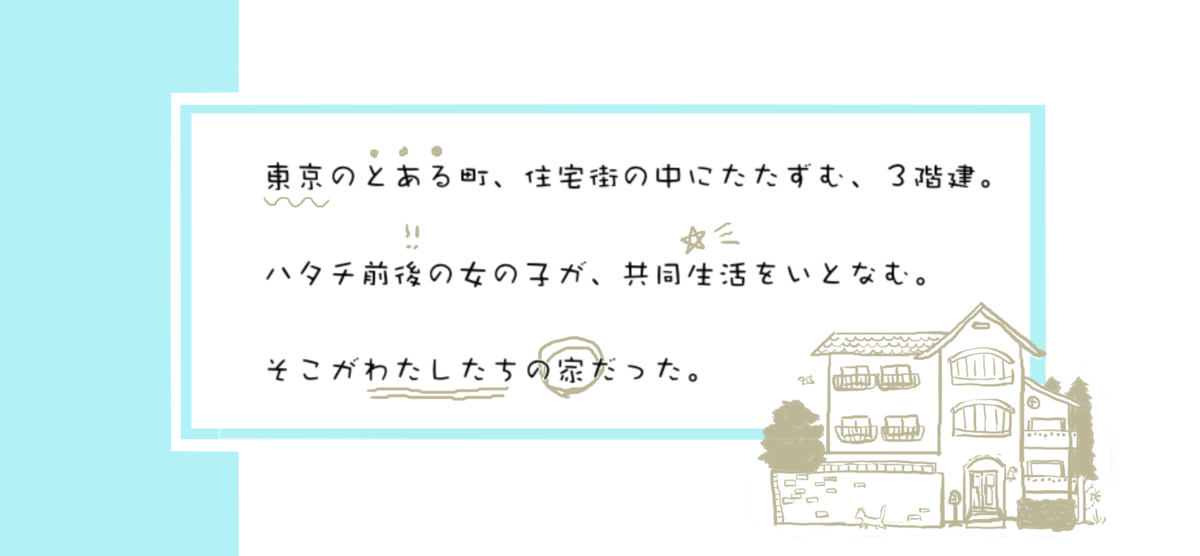
わたしたちが住んでいた寮、つばめ寮は、トイレも食事も洗濯もすべて共同だった。
もちろんお風呂も。
お風呂場には、3〜4人がゆったりと浸かれる湯船があった。お湯を張るのも寮生の仕事で、先に入った人がお湯を張らなければいけない。
このとき、温度設定なんてものはできないから、適当に蛇口をひねって調節しなければならない。古い家や安いアパートだとよくあるが、この方式、家を出たばかりの子は意外と知らないようでよくミスがあった。入寮してすぐの時期は、なにも気づかず、熱湯をなみなみと張ってしまう。
わたしと同じタイミングで入寮した子もこの失敗をおかした。運の悪いことに、先に体を洗い終えた先輩が「熱っ!!!!!!」と叫んだことで、そのミスに気づいた。その子は体に泡をつけたまま、「すみません!!!」とオロオロしていた。まだ先輩にビビっていた時期のできごとである。気を利かせて入れてあげたのに、かわいそうに。
他人とバスタイムを共有して気づいたことがある。それは、体の洗い方にも相当癖があるということ。
当時面白いなと思った人のことは今でも覚えている。
たとえば、髪の毛を洗い終わった後、水気を絞るときに毛先をぴょいっとひっくり返す子がいた。毎回、かならず。くるりん、ぴょいっ。
そうすると水鉄砲のように、水が飛ぶ。
あ、今日もいきおいよく飛んだな、と思う。
だからその子の右サイドで洗う人は要注意である。
もっと要注意なのが、顔の洗い方が独特な子。
彼女はとても姿勢がよく、お風呂用の椅子に腰掛けているときも背筋がぴんっと伸びていた。それはいいが、その姿勢のまま顔を洗うのが問題だった。洗面器から水をすくい、肘をばねのように動かして、水を勢いよく当てる。パシャっ。顔面に対して、垂直に。そう、まるでロボットのように。
あまりにも勢いよく当てるので、はたから見ていて、精神統一でもしているのかなと思うほどだった。
その子の場合は、両サイドが危険だった。
あの勢いで顔を洗うと、確実に水が飛んでくる。
顔に出やすいタイプの先輩からは、明らかに嫌がられていた。込み合う時間帯は、どうしても隣に座る必要があるからである。
しばらくして遠慮がちに洗うようなってしまったのは残念だった。垂直にパシャっと水をかけるの、面白かったのに。
しかし、ひときわ目立っていたのは、全身を石鹸で洗う人。
風呂場に私物はおいておけないので、毎度、各自が洗面器に必要なもの一式をそろえてもっていくのだが、彼女はいつも身軽だった。石鹸オンリー。
髪も、顔も、ぜんぶ石鹸で洗っていく。
そして湯船につかることもなく、ささっと出ていく。
潔い。
口の悪い友達は、彼女のことを「石鹸女」なんて呼んでいた。そう呼べば誰のことだかみんな分かってしまうというのが、寮の怖いところ。だが本人は、まわりから白い目で見られようと、ひそひそとうわさされようと、一向に気にするそぶりを見せなかった。
(長い黒髪は心持ちパサパサしていたが、そんなのは些細なことだったに違いない)
世の中にはいろんは洗い方がある。十人十色。
銭湯では許されないだろうが、寮ではこっそりじっくり観察ができた。

***
ある寒い冬のこと。
その日は、つばめ寮祭というイベントがあって、わたしは自治会の一員として運営やら片付けやらで1日忙しくしていた。ちょっとしたお偉いさんや男子寮の寮生も呼んで、飲めや食えやの大騒ぎ。ゲストの方々をお見送りして、やっと片付けが終わったのはもう日付が変わる頃だった。
ふだんならもうお風呂には入れない時間だった。近隣住民のことを考えて、23時になったら自動でボイラーがとまるようになっていた。
しかしその晩は寮のために働いたということで、自治会メンバーは特別にお風呂に入ることを許された。寮長さんから、「さっさと入ってこい!今ならまだあったかいぞ!」とけしかけられながら。
祭りの後だ、みんなお酒も入っていて、だいぶ陽気だった。
「はーい!」「やったーっ」「ありがとうございまーす!」
いい返事をして、ギャーギャー騒ぎながら風呂場に向かった。
地下の風呂場へと続く階段は冷え切っていた。脱衣場にも暖房はない。
夜が更けて、一段と気温が下がったような気がした。東京にも雪が降るんじゃないかと思った。
「寒い寒い!」
「はやく入ろう」
みんなぽいぽいっと服を脱ぐと、浴室になだれ込んだ。他の寮生がさっきまで使っていたからだろう、まだ浴室はあたたかくて、白い湯気が充満していた。
「やったー、まだあったかい!」
シャワーから出るお湯はあたたかくて、一同ほっとした。今日の疲れを洗い流そう。
しかし、その幸せは長くは続かなかった。
23時になったら自動でボイラーが止まる。
無情にも、その設定は変更されていなかったのだ。
誰が一番先に気づいたのかは覚えていないが、とにかく誰かが声をあげた。
「やばい、シャワーの温度が下がってきた!」
言われてみれば確かにさっきより温度が低い気がする。いやな予感がした。まだ髪の毛に泡がたくさんついているというのに、このまま水になってしまったら……。
「あ、こっちのも冷たくなってきた」
「もしかしてボイラー止まってる?」
「まじ!?」
最悪な事態に気づき、みんなが大慌てになった。とにかく少しでも温度を感じられるうちに洗い流してしまわないといけない。貴重なお湯は、一秒ごとに、大量に、失われている。シャワーの設定温度を60℃まであげても、どんどん温かみが感じられなくなってきた。
「さむーい!!!!」
「冷たい!!!」
喚いてものろっても、悲しいかな、最終的には完全に水になった。真冬の夜に冷たい水をあびる。こんなの修行に他ならない。1日頑張った体に、冷たい水が染み入る。ボイラーよりもうるさい乙女たちの叫びが響き渡った。
もし、これで湯船がなかったら、自治会メンバーそろって風邪をひいているところだった。
幸いなことに、他の寮生が湯を張ってくれていて、栓が抜かれないまま、まだ湯船にたっぷり湛えられていた。みんな湯船に浸かることだけを楽しみになんとか修行を終え、ひとり、またひとりと湯船に飛び込んだ。
「「「「あったか〜〜い!!!」」」」
冷たい水に打たれた後のあたたかなお湯は、この世のものとは思えない気持ち良さだった。芯まで冷えた体がほどけていくようだった。
数人しか入れない湯船に、なんと同時に九人も入った。ぎゅうぎゅうに入っているのが自分たちでもなんだか面白くなって、大声で笑った。九人の笑い声が天井や壁にこだました。
「なあ、これ記念に写真撮らん?」
誰かが言い出して、みんながいいね、いいねと賛同した。こんな楽しい瞬間、このまま記憶の海へと流し去ってしまうのはもったいない。
後輩を呼び出して、カメラマンをお願いした。後輩はカメラを受け取った後、何か言いたそうな顔をした。ファインダーを覗きながら、何度も「本当にいいんですか?これ、撮るんですか?」と確かめてきた。
そりゃそうだ、ふつうに考えて、風呂場である。流出したら大問題の写真になる。
それでも妙な連帯感と高揚感に、今ここで撮らなくてはいけない気がしていた。大丈夫大丈夫と押し切ると、後輩はやっと頷いてくれた。
「じゃあいきますよー、はい、チーズ!」
肌色の肉肉しい写真が撮れた。
その写真を見て、また大笑い。
後輩はまだ困ったような顔をしていたが、わたしたちは大満足だった。冷え込んだ夜の街にも、わたしたちの笑い声が漏れていたに違いない。
それに、それはある意味流出しても平気な写真だった。狭い湯船に大勢で浸かったおかげで、大事なところはしっかり隠れていたのだ。
みんなの赤く上気した顔だけが、もくもくとした湯気の中にうかんでいた。
***
あのときの写真は、携帯電話をかえるタイミングで無くしてしまった。でもそれでよかったのかもしれない。あまりにも肉肉しい写真だったもの。
それでも、シャッターを切った瞬間に、ちゃんと心の中に焼きついた。
みんなでお風呂に入ることが日常だったなんて、今のわたしからすると、ほんとうに非日常。文字通り、裸の付き合いだった。
たまに大勢でお風呂に入る楽しさを求めて銭湯に行ってしまう。
だけどやっぱり銭湯には他人しかいなくて、全然別物だと気づく。
冬至の日には寮母さんが気を利かせてくれて、柚子がごろごろ浮かんでいたっけ。
わたしたちにとっては半分ボールみたいなものだったけど。
——今度は柚子風呂、再現してみようかな。
↓トイレや洗濯室が共同だったことについてのアレコレ